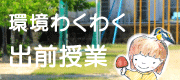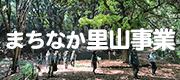市民の板書術(21)「フサホロホロチョウ理論」2019.02.
少人数の話し合いで「動物の名前」をたくさん挙げる場面がありました。グラフィッカは「ゾウ」「ウサギ」「カブトムシ」といった発言を箇条書きで書いていきます。そんな中,一人の参加者が「フサホロホロチョウ!」と言いました。グラフィッカは「なんだ?その面白げな名前は?冗談かな?まさかそんな動物がいるの?」と面白がったり悩んだりしてるうちに,つい他の発言を書き漏らしてしまったそうです。
フサホロホロチョウは,キジ目ホロホロチョウ科に属する実在する鳥です。アフリカ中央部などの乾燥した地域に生息し,草や虫やトカゲとかいろいろ食べます。首から上はコンドルやハゲワシみたいで,体の前半分はコバルトブルーと黒と白のストライプでフサフサ,後ろ半分は黒地に白のドット柄。大人になると目が真っ赤になります。食用に飼育されることもありますし,危険を感じたら走って逃げるので「アフリカの派手なニワトリ」といった感じです。
話し合い中の発言で知らない単語が出てきたらどうするか?例えば専門用語。一般的でない用語が出てくることがあるでしょう。もしくは地名。地元の人しか知らない字名などです。他にも関係者のお名前や地域の伝統行事の呼称,その団体の過去の出来事などいろんな場合が考えられます。
そんな「知らない単語」が出てきた時にやるといいことがあります。
1. とにかく聞こえたままを口に出して繰り返す。
聞き間違いがないか確認できます。また,きっとそのそぶりで「あぁ,この人は知らないんだな」と出席者に伝わりますし,それはよいことだと思います。場合によっては補足説明をする出席者もあるかもしれません。
2. 他の出席者の表情を確認する。
他の出席者がその単語を知っているのか,知らないのか,表情を見渡して確認します。板書役以外は全員が知ってそうな場合,一部の人が首をひねって知らない様子を示している場合,全体的にキョトンとしてほとんどの出席者が知らなそうな場合等,いろいろあると思います。その様子次第で,対応も少し変わります。
3-1. ほぼ全員がわかっている様子で,かつ他の発言もどんどん出てきて忙しい場合。
とにかく聞こえたままをひらがなでもカタカナでも書いておき,次の発言に備えるのがオススメです。書いておけば,後で余裕ができた時に確認できますし,板書役からの質問で議論をスピードダウンさせるのももったいない話です。
3-2. ほぼ全員がわかっている様子だが,他の発言も少なくそれほど忙しくない場合。
一旦,ひらがなかカタカナで書きとめます。その意味や漢字での書き方などを出席者全体から教えてもらいながら,正しく書き加えます。教える&教えられることで出席者との関係性が強められることも多いですし,その単語の説明をやりとりする中で新しい意見や発見が得られることがあるためです。
3-3. わかっていない様子の人が複数もしくは大勢いる
こちらもとりあえず書くのですが,引き続き発言者に補足をお願いし,その説明や語句の定義などを少し小さめの文字(色を替えてもよいでしょう)で書き加えます。出席者が知らない状態で話し合いを進めることも難しいので,情報共有のためにもその単語の確認を行います。
この,知らない単語が出てきたときの対応は「フサホロホロチョウ理論」と呼ばれています(たぶん3人くらいに)。
むしろ,地域の課題を掘り下げる会議や団体のミッションを言語化する会議では「知らないこと」が話し合いを促進することもあると思います。ただし,スピード重視で忙しい会議なのであれば,その分野や経緯を理解している進行及び板書役が適任と言えます。