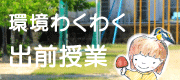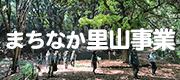人には、かたつむりとの相性とでも言うべきものがあるような気がします。
今回は私の独断と偏見に基づき、かたつむりとの相性が良い人のポイントを
3点にまとめてみます。

1つ目は、待つ力。
かたつむりは、動きがゆっくりです。
長いあいだ殻に引っ込んでしまうこともあります。
何か観察したい行動があっても、早く姿を見たいとか、早く動いてほしいなどと
思って無理に急かすと、むしろ逆に殻に引っ込んでしまいます。
興味を持った対象をじっくり待って観察できるという人は、
かたつむりを見ていても飽きることはないはずです。
2つ目は、雨を楽しむ才能。
雨の日は、外で遊びづらくなります。
ですが、たとえば子どもは、水たまりをチャプチャプしたり、
雨の音を楽しんだりするのが大好きです。
子ども時代に雨の日を楽しいと思えた人は、
かたつむりと出会う機会も多かったのではないでしょうか。
3つ目は、小さなもの、弱いものへの関心。
かたつむりは、ゾウのように大きくも、ライオンのように強くもありません。
軟らかい身体はもちろん、殻だって人の手で簡単に壊せるくらいの薄いもの。
多くの動物の餌になってしまう小さく弱い生きものです。
そのような小さなもの、弱いものに関心を持てる人は、
かたつむりとの相性もさぞ良いことでしょう。
「待つ力」「雨を楽しむ才能」「小さなもの、弱いものへの関心」
こう考えると、かたつむりと相性が良い人って、
なんだかおとなしい人なんじゃないかと感じます。

ところで、民俗学者の柳田国男は「でんでんむし」「まいまい」のような
かたつむりを表す方言がかつて多様だったことを明らかにしています。
柳田は「デェラボッチャ」「マイマイドン」「カッタナムリ」「ツングラメ」
「イヘカエル」「ゼンマイ」など、全国各地のかたつむりの呼び名を
240種類以上も収集しました。
そして、これほど方言が多様化した理由を「童児の力」だと言っています。
子どもたちが「つのだせ、やりだせ」のようなわらべ唄を通して、
かたつむりと遊びながら呼び名を多様化させたと言うのです。
つまり、かたつむりともっとも相性が良いのは、どうやら子ども。
そう考えると、上に挙げた3点も「おとなしい」というより、
むしろ本来は「こどもしい」(?)性質なのかもしれません。
【参考文献】柳田国男『蝸牛考』岩波文庫