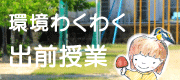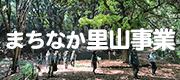かたつむりやなめくじの体は、ぬるぬる、ねばねばの粘液でおおわれています。
彼らの体には、どうしてそのような、ぬるぬるねばねばの粘液が必要なのでしょうか。
理由は1つではありません。
ざっと思いつく、主な理由を挙げてみます。
▼体の水分が逃げないようにする
陸上に進出した貝類であるかたつむりにとって、乾燥は大敵です。
水分は、空気中に蒸発してしまうこともあれば、乾燥した地上に浸透してしまうことも
あります。粘液があることで、水分が蒸発しくいように、浸透しにくいようになります。
▼陸上を移動しやすくする
かたつむりは這う時に、粘液をうまく利用しています。そのため、這ったあとは粘液だけが
きらきらと残されます。
かたつむりの這い歩くメカニズムは、それだけで論文が書けてしまうほど謎めいています。
いずれにせよ、地上をすべるように移動できるのも、壁や葉っぱの裏側などにもぴったり
くっついて移動できるのも、ぬるぬるねばねばした粘液の性質のおかげなんです。
▼外敵などから逃げる
外敵におそわれたときなどには、多量に粘液を分泌します。
このため、なめくじをピンセットなどの道具でつまもうとしても、つるつるすべってしまい
ます。

くっつけたり、すべらせたり、それ自体ふしぎな性質がある粘液。
粘液には酵素なども含まれていて、傷を修復したり、雑菌から身を守ったり、汚れを
つきにくくしたり、上で紹介した以外にもさまざまな役割があると考えられています。
けれど、こうした粘液の機能は、人間にとってもなじみのあるものです。
目や鼻などを乾燥から守ったり、異物が入らないようにしているのも、粘液です。
口や消化管の内側も、粘液でおおわれています。粘液がなければ、胃は自分の胃酸で
溶けてしまいます。
もっとも、人間は歩くときに粘液は不要です。
そしてもうひとつ、かたつむりならではの、粘液の大事な役割があります。
それは、殻のフタとしての役割です。

かたつむりは休眠するとき、殻の出入り口に粘液の膜を張ります。
この粘液は、水分が蒸発するとエピフラムと呼ばれる白い薄膜に変化します。
このエピフラムが、殻のフタになるのです。
(エビフライではありませんよ。エピフラムです)
このエピフラムには接着力があるので、壁や木の枝、葉の裏などにくっついたまま、
休眠することができます。
冬眠など、長期の休眠の際には、さらに何層もエピフラムを張って、乾燥から身を
守ります。

さらに言えば、かたつむりの粘液の機能は、人間生活にも応用されています。
エピフラムは強い接着力のある一方、水に濡れるとすぐにやわらかくなり、
きれいにはがせます。この特徴を生かした接着剤が開発されているそう。
また、かたつむりの粘液を使った化粧品もあるというから驚きです。
(効果のほどは定かではありませんが、保湿力はありそうです)
ぬるぬるねばねばは、かたつむりやなめくじが嫌われてしまう理由の1つでも
ありますが、かたつむりにとっては生死に直結する大事なものです。
その点、どうかご理解いただければと、かたつむりを代理して、お願い申し上げます。