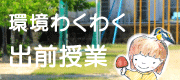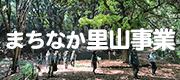映画「シン・ゴジラ」で「政治家の責任の取り方は己の進退だ」というセリフがありました。「責任をとること」=「辞めること」だったらシンプルですが、実際はそれだけではありませんよね。
先日の環境保全活動の研修会でも、トラブルを起こした後の「責任の取り方」が話題になりました。「責任を取る」という言葉には重たくてしんどい、時には悲壮感あるイメージがありますね。
でも、具体的なタスクの集まり、と捉えた方がいいんじゃないかと思っています。
英語では「責任」に三つの単語があるそうです。それを手掛かりに整理しました。
森の保全活動のボランティアでうっかり道具を壊してしまった(例えば唐グワの柄を折った等)。そんな場面を事例に考えてみます。
(今回、「誰がそれをやるのか?」は一旦、置いておきます。団体自体、団体の代表者、指導していたリーダー、壊した本人など、状況によって様々です。)
遂行責任(レスポンシビリティ)
遂行責任とは、約束や予定を果たすための取り組みです。ボランティア活動ではノルマや納期がないことが多いので、この責任はあまり大きくない気がします。それでも、その日の作業に区切りをつけ、次回以降も活動を続けていくためにはいくつかやることがあります。
- 壊れた道具を安全な場所に移す。
- その道具が無くても可能な作業の段取りをする。
- 後日、道具を修理する、もしくは適切に処分する。
- 新しい道具を購入し、使うための準備をする。
- 道具の使い方や注意点を他のボランティアに周知する。
説明責任(アカウンタビリティ)
説明責任とは、トラブルの原因と今後の対策を説明することです。目的は再発防止。以下のような取り組みを行います。
- 道具を壊したことを認め、状況を周囲に伝える。
- 起きた経緯や原因を説明し、記録する。
- 再発防止策を考える。
- 必要に応じて、地権者や発注者、助成元に報告し、指示を仰ぐ。
- 必要なら是正報告書を作成し、安全管理ミーティングを開く。
賠償責任(ライアビリティ)
賠償責任とは、損害を受けた相手に補償することです。ボランティア活動中に起きたトラブルの賠償責任を個人に負わせることは、よっぽどの故意や悪質でない限りありません。第三者に損害を与えた場合でも、団体が加入する賠償責任保険で金銭部分はカバーされるはずです。それでも細かな部分や感情の部分で、「賠償責任」的な動きは残ると思います。
- 他のボランティアや関係者に声がけやお詫びをする。
- 負傷者が発生した場合は謝罪する。
- 傷害保険や賠償責任保険の手続きを行う。
政治家の「辞める」=「責任を取る」という考え方がどれにあてはまるかよくわかりませんが、とにかく「約束や予定を果たすこと」「再発防止を心がけること」「損害を受けた人が補償されること」を考えたいものだな、と思います。