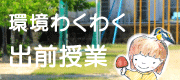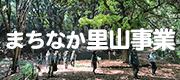志賀島縦断ウォーキングツアー中、イノシシの子ども「ウリボウ」が私たちの目の前を通り過ぎました。
右手の斜面をズドドドッと駆け下り、道路を横切り、左手の谷へ降りていきました。
「イノシシが見れた!」と喜ぶ声もありましたが、運営側としては一瞬身構える場面ですね。
野外活動の安全管理では、イノシシやシカ、サルとの遭遇も注意したいところ。
実際、最近の福岡市内のニュースでも
2024年8月 片江展望台でイノシシにかまれる事故(福岡市城南区)
https://www.youtube.com/watch?v=o8-SNzn5GHw
(2024.11.24.閲覧)
2024年11月 内野中央公園で男児がサルにかまれる事故(福岡市早良区)
https://www.youtube.com/watch?v=HQew2nG2b3k
(2024.11.24.閲覧)
などがありました。
九州にはクマが生息していませんが、クマ対策が必要な地域ではよりシビアかと思います。
環境省のウェブサイトには、イノシシによる人身被害の統計が掲載されています。
https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs4/index.html
(2024.11.24.閲覧)
この統計には「狩猟や捕獲作業等に伴う事故」を除いた数値が記載されています。つまり、登山、犬の散歩、農作業中の事故などが対象。それでも2~3年に1件程度の死亡事故が報告されています。
狩猟にからんだ事故を含めるとしたらかなりの数になるかもしれません。
イノシシ被害防止についての具体的な資料としては以下が参考になります。
復興庁「避難12市町村における鳥獣被害対策」
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/wildlife/20190118111241.html
(2024.11.24.閲覧)
※ページ中程の「福島県避難12市町村イノシシ被害対策技術マニュアル」
130ページ以上にわたる詳細なマニュアルです。(余談ですが、原発事故と避難指示にともなってこのような状況が起きていることを、知っておきたいですね)
野外活動の安全管理としては、VI章の「人身事故防止マニュアル」とその後の事例集が特に参考になりました。
個人的に付け加えるなら「獣道を見分ける目」を養いたいと感じています。
道路や登山道と交わるように獣道の「断面」が出てくることがあります。うっすらした踏み分け道だったり、筋状に落ち葉が踏まれて地表が出ていたり、ヤブがかき分けられていたり…。
明らかにわかる獣道は判断できるのですが、気付けていないものも多そう。
下見の時など、気を付けてチェックし、事前の注意やガイド等に活かせたらと思います。