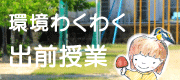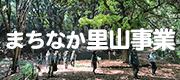私は現在大学4年生。よく大学のキャンパスに生息しています。
家にいるより、外でいろんなエネルギーに当たっているほうが身体が喜ぶみたいです。
私が通っている北九州市立大学 北方キャンパスは、小倉競馬場と自衛隊基地に挟まれているたぶん日本でここだけのキャンパスです。まわりはモノレールの沿線ということもあり、住宅街のなかの、かなりコンパクトなキャンパスでもあります。
そんな小さなキャンパスではありますが、ちょうど中央あたりに広々とした芝生エリアがあります。またそこを囲むようにメタセコイアの木々が連なり、並木道のようになっています。

このメタセコイア並木は夏は通行人を覆う陰となってくれて、秋になると美しいオレンジ色に染まるんです!ここで写真を撮りあう学生たちもたくさんいますよ!
また芝生エリアにはキャンパスのシンボルツリーとしてかまえているヤマモモの木や、チューリップのような葉の形がかわいらしいトウカエデなど、いくつもの種類の樹木が見られます。


私もひとりでこの周辺のベンチに座って本読んだりパソコンを使ったりもするし、
芝生の上で友達とごはんを食べたりすることもあります。
ほかにも、地域の子どもたちのプレイパークの場所になっていたり、竹でドームをつくる集団(?)がいたり、ジャグリング(?)を楽しむ学生もいたり、コーヒーを振る舞う青空喫茶店がオープンしていたり…
そんな光景を見ていると、大学のキャンパスってみんなに開かれた公園のような、コミュニケーションがぽつぽつと生まれる場所だなあと思います。安らぎを与える個人レベルの価値を超えて、対話が生まれる場所。空が見えてオープンな場所だからこそ話せることもあるのではないでしょうか。それが私はとても素敵に思うのです。

(この日は夏休み期間中で人はあまりおらず…。
いつもはお昼休憩の時間などベンチが満席になります。)
数か月前、環境再生・緑地管理のエキスパートである鳥取大学名誉教授 日置佳之先生が登壇された「大学キャンパスの緑地管理」をテーマにした学内特別講義に参加しました。
そこで日置先生がお話されていたのが、
キャンパス内の緑地管理で大切にしたい3つのことは、
①緑陰をつくる(傘状の木陰をつくる樹種を選ぶ)
→これによって体感8℃もちがう!
②生物多様性を高める
→地域(ここでは北九州市)にもともとどんな植物が自生していたかをわかるようにすることが大切!
③四季の変化が感じられるようにする
→落葉樹や多年草を混合させるとさびしい風景になることなく、四季を楽しめる
ということ。
緑をつくることでめちゃくちゃいいことがあるじゃないか!とキャンパス緑にありがたみを感じました。

そして、このキャンパス緑地の管理を防災センターの方だけでなく、大学の構成員(学生たち、教授、職員)や地域の方々と行うことで、そこでもコミュニケーションが生まれるとお話されていました。
実際に、鳥取大学では実技科目として、落枝ひろいや芝生拡張プロジェクトなどもおこなっているそうです。それらは自分たちでキャンパス緑地管理を行ったという達成感にもなりますよね。
私の担当の教授がこれから「キャンパス緑のマップ」や「樹木のネームプレートづくり」をするプロジェクトを始めるので、わたしもそれに参加します!
次回のメルマガでは、そのプロジェクトの進捗状況や、新しく感じた『キャンパスの緑』の価値についてご紹介できたらと思います。みなさんも、ご近所にある「キャンパス」にぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか!