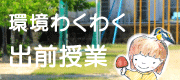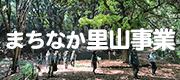森の落ち枝や剪定枝を集めて焚き火する時。
枝の中には結構な水分が残っています。
火にくべていると、枝の中の水分がグツグツと煮えて、道管(水分を吸い上げる管)や師管(養分を行き渡らせる管)を通って、手元の「木口(こぐち)」、つまり「枝を切った断面の部分」から出てきます。
蒸気のような気体がシューっと出てきたり、ブクブクと泡がたったり。蒸気や泡がなくても熱々なこともあります。
木ってやっぱり「管(くだ)」なんですね。
長い枝の手元を火から離れているからと安心して掴もうとしたら、うっかり熱々の木口で火傷するかもしれません。ご注意ください。
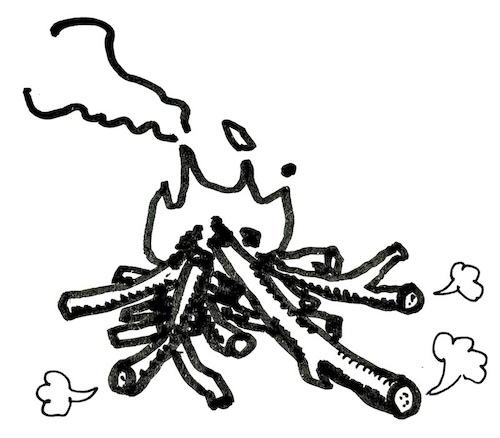
そんな注意点もありますが、森で拾った落ち枝や、森の手入れで発生した剪定枝、枯れ枝などで焚き火をするのは、森のエネルギーを有効活用しているような、ちょっとだけサバイバル体験をしているようなヨロコビがあります。
「これ燃えるかな?」と考えながら落ち枝を集めたり、手頃な大きさに切って太さごとに揃えたり、燃えやすいかたちに組んだりして、焚き火を楽しみたいと思います。
かなたけの里公園で行っている「はじめてのノコギリ・はじめてのたき火」
2023.11.15の様子 http://www.greencity-f.org/blog-post/376442
2022.12.7の様子 http://www.greencity-f.org/blog-post/373332
たき火関連の過去のコラム
第85回「焚き火と煙」2024年2月 http://www.greencity-f.org/blog-post/380540
第68回「風速5.0m/s」2021年12月 http://www.greencity-f.org/article/16445161.html
第58回「強風と乾燥時には焚き火をしない」2021年2月 http://www.greencity-f.org/article/16361101.html
第25回「着衣着火とSDR」 2018年1月 http://www.greencity-f.org/article/15862131.html
第24回「枝や串のこと」 2017年12月 http://www.greencity-f.org/article/15849816.html