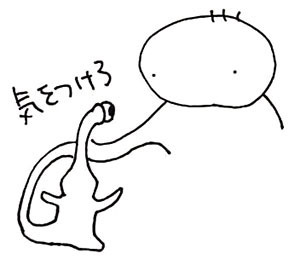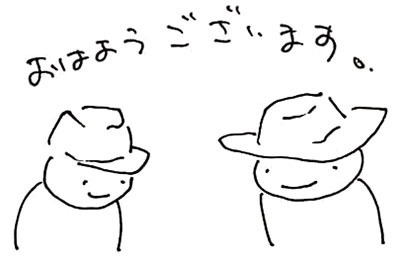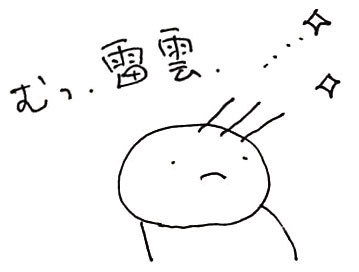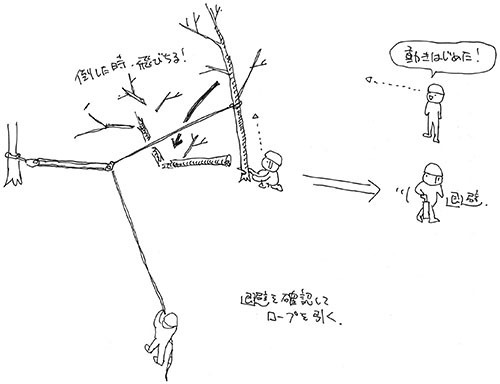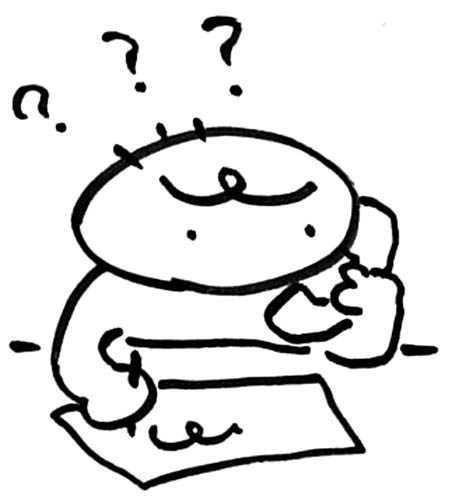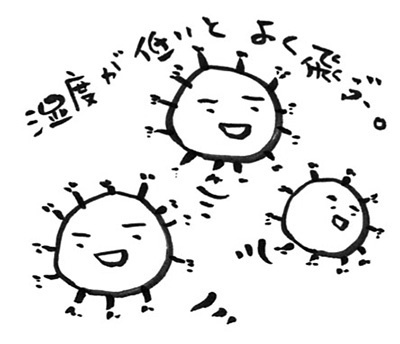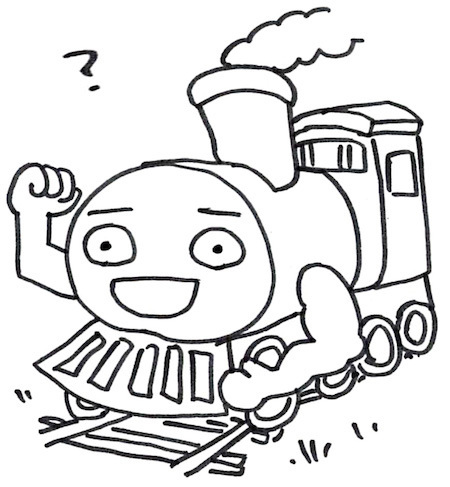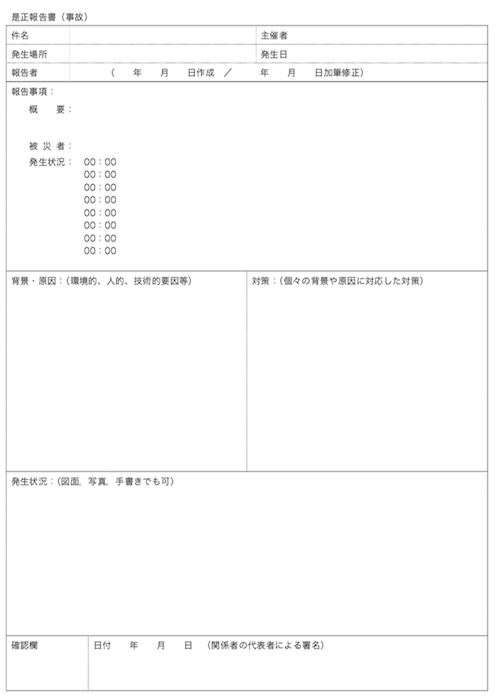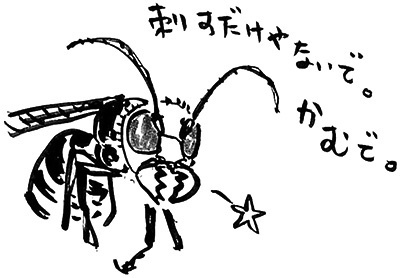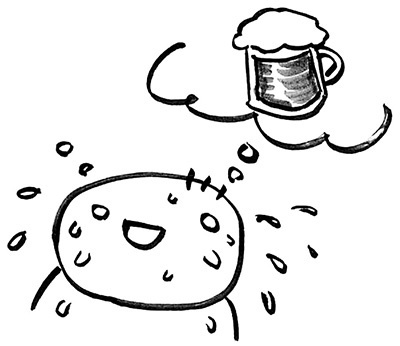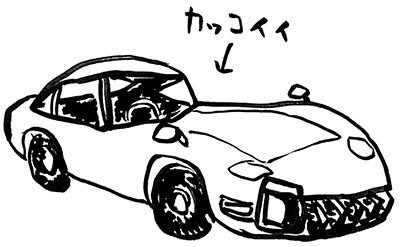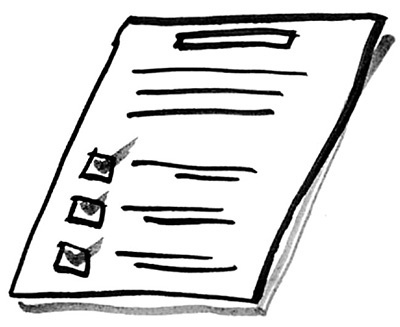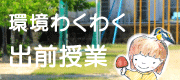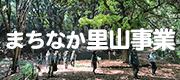今年12月1日から「ながら運転」が厳罰化,違反点数は「携帯電話使用等(保持)」が1点から3点に,「携帯電話使用等(交通の危険)」が2点から6点になりました。6点と言えば一度で免停です。
「ながら運転」に関する警察庁の発表では,スマホ等を見ていたことによる交通事故の件数は増加傾向。交通事故全体の件数は減少傾向なのに,です。さらに,スマホ等見ていなかった場合の事故と見ていた場合の事故を比べると,死亡事故の確率は2倍以上になるらしく,事故の深刻度が高いそうです(平成30年実績)。
思い出されるのは2016年10月に起きた事故。トラックのドライバーがスマホゲームのポケモンGOをやりながら運転し,集団下校中だった小学生をはね,4年生の男児が亡くなりました。
ポケモンGOは世界的なブームになりましたが,アメリカでは交通事故との関係を調べた調査も報告されています。"Death by POKEMON GO(ポケモンGOによる死)" というなかなかストレートな表題のレポートです。
アメリカのパデュー大学の二人の教授が,ポケモンGOリリース後,インディアナ州ティピカヌー郡でに起きた交通事故,約12,000件を調査・分析したものです。「ポケストップ」の周囲100メートル以内で起きた事故を集計したり,走行しながらでも利用できる「ポケストップ」とそうでない「ポケジム」を比較したりしつつ,結果,約12,000件の事故のうち134件が,ポケモンGOが原因だったとしています。これから「推論」すると全米におけるポケモンGOによる事故は14万5千件以上,死亡件数は256人になるとのこと。
あくまで推論だと思いますが,ちょっと衝撃を受ける数字です。これはポケモンGOによる影響だけを考察していて,メールやSNS,動画やコミックなどのアプリによる影響は含まれていないのでなおさらです。
私自身が気をつけたいのは,Googleマップなどのナビアプリの使用です。目的地の入力や高速を使うか使わないかの条件設定を済ませてから,車を動かすように徹底しないといけませんね。
厳罰化がはじまった2019年12月上旬のある日,福岡市中央区薬院の交差点で信号待ちをしてる間になんとなく通り過ぎる車のドライバーを見てました。20台ほど通り過ぎるのを数えた中で1人,スマホをハンドルに重ねて持ちながら運転してる人がいました。
うーん,意外とまだいるのかもしれません。
参考文献:
日本経済新聞 2018/10/26「愛知・ポケGO事故2年 遺族『ながらスマホやめて』」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191201/k10012197481000.html(2019.12.19.閲覧)
警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html(2019.12.19.閲覧)
Mara Faccio, John J. McConnell (2017) Death by Pokémon GO: The Economic and Human Cost of Using Apps While Driving. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3073723(2019.12.19.閲覧)
GIZMODO 2017/11/28「ポケモンGOで増えた米国での交通事故は、推定約10万件以上」 https://www.gizmodo.jp/2017/11/pokemon-go-caused-traffic-accidents.html(2019.12.19.閲覧)