理事の志賀が安全管理について感じたこと、考えたことを書いています。
理事の志賀が安全管理について感じたこと、考えたことを書いています。
年末ということで、2025年の事故事例収集を振り返ってみたいと思います。
私たちの事故事例収集は、主にメディア報道をもとに「なんとなくグリーンシティ福岡の活動にも関係してきそうだな…」というものをメモにして、共有ドライブに保存するというスタイル。
今年は49件の事故事例を収集しましたが、ほとんどをスタッフのしおさんが集めてくれました。ありがとう!
以下、目立った事故とそれに対するコメントです。
伐採・剪定中の事故(10件)
「のり面で作業中に15mの木の下敷き(70代男性)」
「ボランティアで木の伐採中に脚立から転落(70代男性)」
「ヘルメットなどの安全対策を取らず伐採木と接触(60代男性)」など
今年も残念ながら、伐採中の木との接触や転落などの事故が報道されました。メディアで取り上げられる場合、ほとんどが死亡事故です。あらためて基本的な安全対策の大切さを実感します。
また、プロ・ボランティア問わず、ご年配の方が事故にあうケースが目にとまりました。これは裏を返せば、そうした世代が林業や地域活動を支えている、ということでもあります。安全の仕組みや役割分担を考える必要性も感じます。
焚き火やBBQからの火災(9件)
「集めた枯草を燃やし風にあおられ、畑4haを焼失」
「伐採した木を燃やした際に延焼し、山林火災565ha」
「キャンプ場で焚き火が燃え移り、芝生広場1,800㎡に延焼」など
焚き火や野焼き、バーベキューの火の不始末による火災が目立ちました。燃えやすい環境での着火、使用後の炭の処理ミス、強風下での作業など、どれもヒヤリとする事例ばかり。人的被害がなかったとしても、自然環境や施設へのダメージは大きく、後悔の残る事故になります。
キャンプブームで火を扱う楽しさが広まったぶん、安全に楽しむための「知識と技術」も併せて広めたいなと感じます。
倒木・落枝による事故(6件)
「公園で約15mのエノキが倒木、雨後、根元から裂ける」
「緑地の園路を歩いていたら、目の前でマテバシイが倒木」
「大通りの街路樹、約14mのケヤキが根元から折れる」など
街路樹や公園樹の倒木・落枝事故も発生しています。台風ではない普通の雨や風でも、腐朽の進んだ木が倒れることがあります。2014年には倒木事故が多発したため全国で緊急点検が行われましたが、木々は成長するので“点検は一度きり”では不十分です。
「身近に緑があること」は、私たちの目指す姿。でもそれは、ただ植えるだけでなく、育てて、愛でて、活用することとセットです。一緒に手入れや見守りをする仲間や担い手が大切だな、と思いました。
ペットとマダニとSFTS(4件)
「飼い犬がSFTSに感染、(茨城)県内2例目」
「飼い猫がSFTSに感染、関東で初めて」
「SFTSに感染した猫を治療した獣医師が死亡、感染の疑い」など
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)は、これまで山歩きや農作業で人がマダニに噛まれて感染する事例が報道されていましたが、今年はペットの感染が目にとまりました。
また近年、都市部でも急増しているアライグマは、マダニを市街地に運ぶ役割を果たしていると指摘されています(アライグマ防除研究会・菊水研二さん)。それは、マダニとペット、あるいは人との接点が増え、SFTSへの感染リスクが高まるということです。特にペットを飼っている&ご高齢の家族がいるご家庭では、注意が必要となってくるかもしれません。
他にも、熱中症、落雷、蜂刺され、川や海での事故がありました。どれも実際に起きたことで、自然と関わる活動をする私たちにとって他人事ではありません。どんなことが起きるかを知っておくこと、語り合っておくことが、安全管理の土台になると考えています。
来年もまた、ほどよくアンテナを張りながら活動を続けていきたいと思います。

展示用に紙粘土で作った「マダニ対策してない人、マダニ対策してる人」
ちょっと時期遅れですがスズメバチの話題です。
韓国・慶北大学校のチェ・ムンボ先生らが、韓国にとっても外来種であるツマアカスズメバチ(Vespa velutina nigrithorax)の防衛行動を観察した2021年の実験を見つけました。「ツマアカスズメバチの巣を棒で叩いて、距離や逃げ方でどれくらい攻撃されるか、いろんなパターンでビデオ撮影しながら数えたよ」というユニークな研究です(リンク先で英文PDFをダウンロードできます)。
面白かったので、ポイントを整理してみますね。
・ツマアカスズメバチの巣、計6箇所を使って、防護服などの安全対策をしつつ棒で刺激した。防護服は白色、頭部に黒色のかつらを装着した。攻撃される様子をスローモーションでビデオ撮影、刺そうとしたハチの個体数をカウントした。
・以下の四つの切り口で攻撃数をカウントし、比較した。
1)「ゆっくり接近」「腕を大きく振りながら接近」で攻撃開始距離を比較。
2)「ゆっくり歩いて離れる」「走って逃げる」で追跡距離を比較。
3)「立ったまま」「しゃがむ」で姿勢による攻撃数を比較。
4)帽子について「着用」「非着用」で攻撃数を比較。
その結果、以下のことがわかったそうです。
・ゆっくり接近したら1mまで攻撃は無かったが、腕を大きく振りながら接近すると3mの距離から攻撃が始まった。巣への接近距離そのものよりも、人の動作の大きさが攻撃の引き金になりやすいと考えられる。
・攻撃開始の後、ゆっくり歩いて離れると5mでも攻撃数は減少せず、10m離れて約半分に減少、100mでも数匹の攻撃があった。一方、走って逃げた場合5mの時点で明確に攻撃数が減少し、10m地点で急激に低下。20m以降では集団攻撃はほぼ解消された。
・攻撃を受けた際、立った姿勢でもしゃがんだ姿勢でも攻撃数に有意な差は無かった。
・帽子をかぶると有意に攻撃が減少した。頭部への攻撃の約75%が帽子によって回避された計算。
短く言うと「走って逃げた方がいい」「しゃがんでも刺される」ということのようですね。
あれ?スズメバチ対策では「ソーッと離れよう」「見かけたらしゃがんで」とよく言われます。
ですが、これらは矛盾してませんよね?場面が違う、ということだと思います。
<1匹で飛んでいる斥候のスズメバチを見かけたら>
・ソーッと離れる
・しゃがんで飛び去るのを待つ
・手を振り回したりしない
<巣から集団で攻撃されたら>
・走って逃げて巣から距離を取る
・しゃがまない
基本、刺激せずに距離を取ること。
でも、うっかり巣を刺激してしまった場合には、すぐに走って逃げる。
この「切り替え」が大事ですね。
秋はイベントや活動が増える時期。仕事や活動の段取りもついバタバタとあわてがちになります。でもそんなときこそ「安全のための時間」を意識して取ることが大切ですね。
グリーンシティ福岡ではよく「イベント前ミーティング」を実施します。土日の開催だったらその直前の金曜や木曜日。担当スタッフで、準備物の確認、当日の流れ、スタッフの移動手段や集合場所、想定されるリスクなどを共有します。15〜30分程度。短時間でもあらためて確認しておくと不安が減り、余裕が生まれます。
また、当日のイベント開始前にも手早く、参加者のキャンセル状況や進行の流れ、役割分担などを確認します。時間にすると5〜10分程度。ただ、会場設営や早く来た参加者への対応でバタバタしてしまい、やらないままイベントをスタートさせてしまうこともあり…反省中。イベント中に「あれ、誰が何を担当するんだっけ?」となると、余裕も減り、安全管理上もよくないですね。
特に、参加者が多いワークショップや集客イベントへの出展など、流動的かつ臨機応変な対応が必要な現場だと、全体が見渡せなくて「軽いパニック状態」で運営してしまう場合も。そんな現場ほど開始前に「今日はどんな危険がありそうか?」など、全員で共有しておくといいですね。落ち着いて行動でき、事故の芽にも気づきやすくなります。
安全対策のために必要なのは、特別な道具や難しい技術だけではないと思います。1〜2分でも、立ち止まって状況を確認する「時間」こそ安全のカギかと。
私たちもカンペキとはなかなかいきませんが、そういう「安全のための時間」を活動や業務の中に組み込んで、それをやるのが当たり前な雰囲気を育てていきたいと思っています。
先月(2025年9月)、東京の国立オリンピック記念青少年総合センターで「CONEリスクマネジメント講習会講師養成会」を受講してきました。
CONE(自然体験活動推進協議会)は、自然体験活動の推進と普及を行う全国組織です。特に安全講習会や安全管理担当者の養成講座に力を入れていて、以下の研修と資格付与を行なっています。
<資格>
リスクマネジメントディレクター
___活動現場ごとの安全管理責任者、事業担当者
リスクマネジャー
___組織や団体の安全管理責任者
<研修>
リスクマネジメント講習会(2.5時間)
___広く一般を対象にした安全管理の在り方を知る講習会。
リスクマネジメントディレクター養成講習会(9.0時間)
___活動現場での安全管理者(事業担当者など)を養成するための講習会。
リスクマネジャー養成講習会(12.0時間)
___活動だけでなく組織運営全体に関する安全管理者を養成する講習会。
私は2018年に「リスクマネジャー」の認定を受けました。
安全管理のコラム第27回「CONEリスクマネジャー養成研修会を受けて」 2018年3月
今回受講した養成会は、広く一般も含めて対象となる「リスクマネジメント講習会」の講師を認定するものです。その「講習会」の内容は下記の通り。
§1リスクマネジメントとは(60分)
§2リスクのチェックポイント(45分)
§3事故事例から学ぶ(45分)
これまで全国で60名ほどの講師が登録されたそう。福岡県内では北九州の玄海青年の家さんが毎年、講習会を開催されていますが、福岡市内で活動する講師はまだ少ないようです。今後はグリーンシティ福岡でも、地域向けのリスクマネジメント講習会を開催していけたらと考えています。
coneの安全管理講習は合宿型の自然体験やキャンプ活動に取り組む自然学校スタッフをイメージしている印象がありますが、もっと幅広い方に知っていただきたいな、と思います。
例えば、
・花や緑に関する活動を行う市民グループ
・公民館でイベントを行う人、学校や幼稚園の教職員や保育士
・企業の社会貢献や地域交流の担当者
・お子さんに自然遊びをさせたい親御さん
などなど。
安全管理というと「難しそう」「責任者に任せる」と思われがちですが、その場にいる人それぞれが自分ごととして捉えた方がリスクを減らすことができます。みんなで声をかけあい、お互いで安全・安心の場を作る文化を育てていきたいですね。
まだ計画中ですが、2026年2月28日(土)に第1回となるリスクマネジメント講習会を福岡市内の会議室で開催したいと考えています。後日、あらためてお知らせします。
2025年6月、福岡市内の浜辺で小学生が亡くなる水難事故がありました。とても悲しい事故です。心からお悔やみ申し上げます。
その後、水難学会が事故原因を調査していたそうですが、調査の様子が、Yahooニュースのエキスパートトピとして速報されました。同学会理事で長岡技術科学大学の斎藤秀俊先生が書かれたものです。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/20f34eafd2d21a946444be15bf85dd41fa539b2e
Yahooニュース「福岡市・三苫海岸での小6男児2人溺水事故 現場の深みと流れを形成する、まさかの淡水」斎藤秀俊(水難学者/工学者 水難学会理事/長岡技術科学大学大学院教授)(2025.08.29.閲覧)
事故の概要や調査についてはリンク先をご覧ください。
記事中では「海底湧水」が影響した可能性も指摘されています。水の流れで深みやハマりやすい場所ができたことは十分考えられます。
個人的な経験では、砂浜の貝殻をテーマにしたオンライン観察会の下見で。スマホで撮影しながら浜辺を歩いていました。陸側から注ぎ込んでいる小さな小川を跨ごうとした時、やわらかい砂地に一気に膝上までハマったことを思い出します。一人だったのでちょっと焦りました。小さなお子さんなら結構怖い深さだったと思います。
このように、湧水や水の流れがあったり、構造物で水が巻いたりする場所は、地面に見えても砂がふわふわしてハマりやすい場所が出来がちです。この時は、撮影しながら足元をよく確認せず近づいてしまいました…。
グリーンシティ福岡は、海や川など水辺の活動は少ないです。
それだけに、思わぬ深みやはまり込む場所には気をつけて下見や活動を行いたい、そして思わぬ事故を少しでも減らせたらと思います。
⸻
余談ですが、記事中に私たちのブログ記事(2014年のもの)を引用いただいています。奈多海岸で海底湧水を採取した記事です。「海底湧水」という語は、同じ「海底から湧いてくる水」と言っても、状況によって性格がだいぶ違ってくるように思います。
Yahooニュース記事の「海底湧水」:
陸地に降った雨が地下水となり、海底の一箇所から流れ出てくる淡水。水量によって深みや流れが出来うる。
2014年のGCFブログ記事の「海底湧水」:
砂浜に浸透した海水が地下水の圧力で再度、押し出されてきた海水。面的に滲み出てくるので深みや流れが出来にくい。
目に見えない地面の下、海底にもいろんなメカニズムがありますね。そんな自然の営みを少しずつでも理解していけたら、と思います。
このコラムもついに第100回となりました!パチパチ!
約10年前にスタート。新人スタッフ向けに安全管理の「言語化」が必要だったというのが動機です。
その頃、露天風呂に浸かりながら、かごしまカヤックス のNさんに「安全はしっかりやったがいい」とアドバイスいただいたこともいい思い出です、笑。後押し、ありがとうございました!
過去の99本のコラムの中から、個人的になんか思い入れのある10本を選んでみました。
読んで役立つかはよくわかりません、笑。お暇なときに、気になるものがあればぜひ覗いてみてください。
第11回「事故事例研究」 2016年9月
決めつけず、落ち着いて、「事実」を確認すること大切。
第33回「SHELモデル」2018年10月
医療分野でよく使われるようですが、野外活動でも参考になります。
第34回「なぜなぜ分析」2018年11月
有効だけど、「人間」相手にどのくらい使ってよいかは…?
第41回「ガイドレシオ」2019年6月
私たちは何人のお客様・参加者を相手にしていいの?
第44回「お互いに声をかける」2019年10月
お互いに目を配れる関係性や場になるよう、心がけたい。
第45回「交通事故のこと(1)」2019年11月
やっぱり一番身近でリスクの高い道具かと…。
第60回「医薬品の製造不正で」2021年4月
製造業の安全管理も参考になります。
第66回「あの猫とあのワニ」2021年10月
もはや猫もワニも忘れられつつある感…。けどキャラって大事。
第78回「『森林ボランティアの安全管理』メモ」2023年6月
イベント登壇をきっかけに、根っこの考えをまとめました。
第96回「ファーストエイドガイドラインに『蜂刺され』追加」2025年3月
やはりポイズンリムーバーは蜂刺されの対応にはならない、と…。
グリーンシティ福岡では、年3回、(一社)福岡市造園建設業協会さんが行う花壇の植替え活動の、現場コーディネートを行っています。福岡市職員のみなさんや園芸福祉ふくおかネット、緑のコーディネータのみなさんと一緒に取り組む花苗の植え替えです。
このような花壇の活動、まちなかですし大きな危険は無いように感じますが、気をつけておきたいこともチラホラ。
特に、一般の方や自転車が通行する歩道・車道に面した場所、木陰が少なくアスファルトの熱が感じられる場所などでは、森や自然の中とは違ったリスクも出てきます。
例えば…
○通行人や自転車とすれ違うときにヒヤリ
○車道側にうっかり道具が転がった
○日差しが強く、熱中症になりかけた
「都市型・まちなかの花壇づくり」での安全対策として、現場の運営者やリーダーが心得ておきたいことを整理してみました。
【作業前】事前準備とオリエンテーション
□ 歩道や車道との境界を確認(見えにくい段差や勾配は?)
□ 道具や荷物の置き場所を決めておく
□ 参加者が通行人や自転車と交差する導線を無くす・減らしておく
□ サインや(必要なら)三角コーン、ロープで作業エリアを明示
□ 視認性の高いベストや腕章などで作業中であることを明示
□ 参加者への道具の使い方、注意事項、体調管理などの説明
□ 初参加者や体調不良者の把握と安全ルールの共有
□ 熱中症予防のため、日陰や休憩場所、お手洗い、自販機などの案内
【作業中】現場での目配りと声がけ
□ 参加者の位置、体調に目を配る
□ 通行人、自転車が近づいたら声掛け、必要なら手を止めてもらう
□ 作業道具や参加者が通行をふさがないよう注意
□ スコップなど作業道具を歩道や車道に突き出さないよう声がけ
□ 車道に近い場合、車両の誘導
□ 参加者への体調管理(水分補給、日よけ)の声がけ
【作業後】撤収と今後の改善に向けて
□ ゴミや道具の置き忘れがないか確認
□ 歩道上の泥や落ち葉、水を清掃して転倒を防止
□ 忘れ物・ケガの有無、ヒヤリハットの共有
□ 改善点等を含め、スタッフふりかえりをKPT等の形式で記録
「一人一花運動」に取り組む福岡市では、ますます花やみどりを通じたまちづくり、コミュニティづくりが盛んになっています。
だからこそ、誰もが安心して関われるようにしたい。
事故を防ぐことも、楽しい活動の一部。そんな考えを大切にしたいと思います。

福岡市役所の花壇は、縁石が斜めにカットされてるのも要注意。上に乗るとうっかり歩道側にひっくり返りがちです(笑)。
救急セットの中身については、このコラム第6回「使える救急セットにする」2016年4月で書きました。
今回は救急セットの中の「テープ類」に注目。
救急セットに入れておきたいテープ類を3種類挙げました。
○サージカルテープ
ガーゼなどを固定するために使います。私たちの活動で考えられるのは、大きめの擦り傷をした時など。傷口をよく洗った後、絆創膏では小さすぎるので、ガーゼをあてサージカルテープで固定。その上から包帯を巻いて患部を保護する、といった場面です。素材や粘着力でいろんな製品がありますが、使うときにパッと手で切りやすいのがよいと思います。
○キネシオテープ(伸縮テープ)
ひっぱると伸びるテープ。筋肉や関節のサポートをするために使います。軽い痛みや違和感への対応に向いているので、私たちの活動で考えられるのは、ガイドウォークやトレッキングの途中で膝が痛くなってきた時など。痛みや違和感を感じる関節を囲って守るように、少し引っ張りながら貼ることで、負担を軽減します。カラフルな製品があるので、私たちはブルーのキネシオテープを手頃な長さに切って救急セットに入れています。
○テーピングテープ(非伸縮テープ)
伸びない、しっかりとしたテープ。私たちの活動で考えられるのは、足首などを捻って、より強い痛みを感じる時。しっかり固定するために使います。捻挫や靭帯損傷、骨折が疑われる場合は「RICE処置(Rest安静・Ice冷却・Compression圧迫・Elevation挙上)」を行いながら、そのうちの「圧迫」としてテーピングテープを使うこともあると思います。一巻、セットに入れています。
いろんな種類のテープがあるので、用途にあわせた使い方を身につけておきたいところ。どの製品もおおむね2〜3年が使用期限となっているので、期限の過ぎたテープを更新する時に、練習で自分に使ってみたり、スタッフ同士でシミュレーション(受傷者役&対応者役)してみるのがオススメ。貼り方の動画などもたくさんあるので参考にしていきたいですね。
ゴールデンウィークですね。
日差しがぐっと強くなってきました。夏というには早いですが、この時期でも突然気温が上がる日があります。身体がまだ暑さに慣れていない「準備不足」のこの季節。熱中症に注意です。
暑さに身体が慣れていくことを「暑熱順化」と言いますが、暑熱順化できていない状態では、汗をかく反応が遅かったり、汗の中に必要以上に塩分を含んだまま排出したりします。
そんな今の時期こそ意識したいのが「電解質」の補給です。
具体的には次のようなミネラルイオンのことで、それぞれ体液の浸透圧を保ったり、筋肉の収縮、神経伝達など重要な働きを担っています。
・ナトリウム(Na+)
・マグネシウム(Mg2+)
・カリウム(K+)
・カルシウム(Ca2+)
・クロール(Cl-)
汗をかくと、これらのミネラルが水分と一緒に体の外に排出されます。特にナトリウムやマグネシウムが不足してくると、足がつったりします。水だけを飲み続けて「低ナトリウム血症」や「水中毒」と呼ばれる状態になると、めまいや意識障害、けいれんなど、より重い症状を起こすリスクがあります。
大切なのは水分と一緒にミネラルを補うこと。スポーツドリンクや経口補水液、塩飴、梅干しなどが適しています。
また、私たちの活動は午前中に行うことが多いので、朝ごはんは大切です。朝食を抜くと、どうしても水分、エネルギー、ミネラルが不足しがち。気温が高い日は、熱中症予防の点で特に意識して朝食をとっておきたいところ。
味噌汁+ごはん+おかずのような和食の朝食は、塩分も水分も、しっかりとれそう。
パンの場合、卵料理やバナナ、牛乳などがあるとよさそうですね。
逆に、菓子パンとコーヒーだけとかだと、エネルギーはとれても、ミネラルが不足しそう。
何も食べない・飲まないよりはいいかもしれませんが、ちょっと心配です。
春から初夏にかけては、暑熱順化できておらず、汗をかくのが下手&余計にミネラルを失いがちな状態。「水だけでなく、ミネラルも一緒に」「朝ごはんをしっかりと」を心がけて、気持ちのよい春〜初夏を安全に楽しんでいきたいと思います。
季節的にはちょっと早いですが「蜂刺され」について。
2017年の本コラム第18回「ポイズンリムーバーを過信しない」では、アメリカ心臓協会(AHA)の「ファーストエイドガイドライン」を引用しました。
その当時、ガイドラインに「蜂刺され」の項目はありませんでしたが、2024年版の更新で追加されたようです。リンクはコチラ:2024 American Heart Association and American Red Cross Guidelines for First Aid
上記リンク先の、「7. Environmental Emergencies」の「7.1 Bee and Wasp Stings」です。
これによれば、アメリカでは蜂刺されによる死亡が年間約60件報告されているとのこと。その多くはアナフィラキシーによるものです。
実際に蜂に刺された時の対応は、これまでと変わらないと思います。10個の対応策が、その「推奨クラス」とともに整理されていました。
COR LOE 内容
1 B-NR 1.アナフィラキシー症状があれば、直ちに本人がエピペンを使用する。
1 C-EO 2.本人がエピペンを使うのが困難な場合、周囲の人が補助する。
1 C-EO 3.アナフィラキシー症状があれば、救急要請を行う。
1 C-EO 4.眼を刺された場合は医療機関を受診する。
2a B-NR 5.針が残っていれば、できるだけ早く引き抜くかこすり落とすとよい。
2a C-EO 6.経口の抗ヒスタミン薬で、かゆみを緩和してもよい。
2a C-EO 7.外用のステロイド薬で、かゆみを緩和してもよい。
2a C-EO 8.刺された場所を石鹸と水で洗うことは合理的。
2b C-EO 9.市販の解熱鎮痛薬で、痛みを緩和させてもよい。
2b C-EO 10.氷や冷却パックで、痛みを緩和させてもよい。
ちなみに、CORとLOEはそれぞれ下記です。
「COR(Class of Recommendation)」=「推奨クラス」
1 強く推奨される(安全で効果があり、必ず行うべき内容)
2a やった方がよい(十分な根拠があり、利益が期待できる)
2b やってもよい(効果はあるかもしれないが、証拠がやや弱め)
3 やるべきでない(効果がない、または有害なので避けるべき)
「LOE(Level of Evidence)」=「科学的根拠のレベル(信頼性)」
A 高度なエビデンス(複数の無作為化比較試験などに基づく)
B-R 中程度のエビデンス(無作為化比較試験に基づくがAよりやや弱い)
B-NR 中程度のエビデンス(観察研究などに基づく)
C-LD 限られたデータ(限られた症例報告や経験的なデータに基づく)
C-EO 専門家の意見(科学的根拠がほとんどないが、専門家の意見として妥当)
野外活動の現場では、どれだけ気を付けても、蜂に刺される可能性をゼロにすることはできません。だからこそ、「もしも刺されたら」の備えをしておきたいですね。エピペンを持っている人は使い方を確認しておく、刺された場合に針をどうやって除去するかを知っておく、アナフィラキシー症状を正しく判断して医療機関へつなぐことができる、こうしたことの積み重ねが大切です。
こうした国際的なガイドラインも参考にしつつ、私たちも知識や対応力をアップデートしていきたいものだな、と感じました。
2025.08.02.補足:ポイズンリムーバーによる処置(suction / 吸引)は、「7.1 蜂刺され」の項目には記載がありません。「7.4 Snake Bite」の項目にあり、評価は下記の通り「やるべきでない」となっています。
COR LOE 内容
3 C-LD 5. 蛇の咬傷に吸引を行うことは有害となる可能性がある。
2月もそろそろ終わり。日中は春らしい日も増えてきましたね。
しかし、この時期はスギ花粉が本格的に飛び始める時期でもあります。福岡市では2月下旬から3月上旬にかけてがスギ花粉のピーク。私も花粉症ですが、目のかゆみやくしゃみよりも、肌の荒れやかゆみが気になるタイプです。
花粉症は単に不快なだけでなく、作業や運転の注意力低下から、安全管理上の課題にもなりえます。例えば…
視界の悪化:目のかゆみや涙で視界がぼやける。
注意がそれる:くしゃみや鼻水で一瞬体の動きが乱れる。
効率や意欲の低下:作業が遅れたり、集中力が削がれたりする。
実際に、花粉症が原因とされる交通事故も報告されています。
・2005年3月(岩手県遠野市):路線バスの運転手が大きなくしゃみをした際、貧血のような状態になり歩道に乗り上げる。
・2017年4月(愛媛県今治市):くしゃみを連発し、対向車と正面衝突。
・2023年3月(大阪市生野区):くしゃみで意識が遠のき、歩道に乗り上げる。
いずれも死亡事故です。運転中に花粉症の症状がひどくなりそうと感じた場合は、安全な場所に停車し、落ち着くのを待つことが大切ですね。
野外活動や体験イベントでは、一般的ですが次のような対策を心がけておきたいところ。
・花粉をつけにくい素材の服装にする。
・帽子をかぶって髪につく花粉を減らす。
・建物に入るときに服を払って持ち込む花粉を減らす。
・こまめな水分補給で喉を潤し、花粉の影響を和らげる。
・トイレや洗面所を使いやすくしておく。
・症状がひどい場合は無理せず休憩する。
・抗アレルギー薬を服用する際は、副作用の眠気に注意。
思わぬ事故を防ぐためにも、また、落ち着いて体験や学びに集中してもらうためにも、花粉症対策を意識したいですね。
2月に入りました。福岡地域でも明後日(2025年2月5日)から数日間、最低気温が氷点下になる予報が出ています。厳しい冬山まではないものの日常的な寒さで体温が奪われ、思わぬリスクにつながることもあります。野外活動中に起こりうる「低体温症」について整理しました。
低体温症というと、吹雪の中の登山や冬の海での事故のイメージですが、身近でも発生することがあります。例えば寒風の中での長時間の作業、濡れた服のまま過ごすこと、栄養(カロリー)補給が不足することなどで、体が芯から冷えてしまったり…。今週は特に冷え込みが厳しくなる予報が出ているため、より意識して対策したいところです。
低体温症が発生しやすい場面について、気温が低いのはもちろんですが、加えて「濡れ」「風」「栄養不足」「活動終了後」などの条件が重なると、注意が必要です。
① 雨や汗で服が濡れたまま過ごす
雨に打たれたり、湿った草の上に座って服が濡れたり。また、厚着をして野外を歩いて汗をかき衣服が湿る、などの場面。先日はアカガエルの産卵場所やベンケイガニの棲息場所として湿地の手入れをしましたが、長靴や胴長をはいていると寒くても結構な汗をかいてしまい、そこから冷えることがあります。
② 風が強い場所に長時間いる
強い風は体感温度を大きく下げます。一般に風速1m/sで体感温度が1℃下がると言われます(実際は湿度や日差しでも変わります)。特に、広場や海ぎわ、川沿いなどは風が吹き抜けるので、知らず知らずのうちに体が冷えます。休憩中に体温が下がることも多いので、下見で風を避ける場所を見つけておくことが大切です。
③ 栄養(カロリー)補給が足りていない
人体は食事で得た栄養(カロリー)から熱を生み出します。活動中にお腹が空いていると体温維持が難しくなります。寒くてお腹まで空いてるとなおさらひもじいですね。朝ごはんをしっかり食べたり、おやつをとれるようにしておきたいところ。加えて、気温が低いと発汗量は減りますが、呼気から水分が失われるため、実は脱水が起こりやすくなります。温かい飲み物をとるのが効果的です。
④ 活動終了後の「急な冷え」
保全作業やウォーキングなどで体を動かしているときは寒さを感じにくいですが、休憩や活動終了後に急激に冷えることがあります。汗をかいた状態で急に止まると一気に体温が下がるためです。寒い時期は、活動が終わった後、防寒着を着たり、風の当たらない場所に移動したりすることで冷えを防ぐことができます。
ということで、野外活動を企画・運営する立場としては、
・気温や雨の動向をチェックしておく
・事前に風をさけられる場所を見つけておく
・活動時間が長い場合、おやつや温かいお茶が飲める休憩をとる
・休憩時や活動後の防寒を呼びかける
・気温や参加者の状況に応じて、プログラム時間を短縮する
などが気をつけたいポイントだと思います。
加えて、グリーンシティ福岡では、寒い時期、携帯カイロ(貼るタイプ、貼らないタイプ)を救急セットと一緒に準備します。建物や休憩場所から遠い活動地であれば、通称「NASA的なアレ」と呼んでいる、表が金色、裏が銀色のアルミ製シート(エマージェンシーブランケット:体温を保持するのに役立つ)もいくつか持っていくことがあります。
雪国に比べたらマイルドな気候かもしれませんが、ここ福岡でも低体温症に気をつけて、寒い時期でも森や自然を楽しめたらと思います。
報道やネット記事で見つけた、森や緑に関する事故、レジャーや体験活動、ボランティア活動の事故など、スタッフが気になった事故事例を収集しています。
私たちが収集した事故事例の件数を振り返ってみると…
2020年度 23件
2021年度 8件
2022年度 24件
2023年度 22件
2024年度 23件
となっていました。
3ヶ月に一度、集めた事故事例をスタッフ4人で読み合わせ、1事例を選んだ上で「事故事例研究」を行なっています。
今年、取り上げた事例は
「もらったミツバにキツネノボタンが混じっていて誤食」
「幼児がマムシグサを誤食」
でした。なんか誤食の事例が続いてますね。その時のスタッフの関心によるのだと思います。
昨年以前は
「湿地作業でのセルカリア性皮膚炎」
「草刈中のツツガムシ病感染」
「スギ伐倒時の下敷き事故」
「脚立からの転落事故」
「木工体験時のノミによる事故」
「磯釣りでの転落遭難」
「電動丸ノコでの切創事故」
「SNSの『炎上』事例」
などを取り上げて、事故事例研究を行なっています。
まずは「報道から読み取れる事実」、
そして「そこから推測できること、考えられること」を整理した上で、
「事故を起こさないための対応・対策」を考える、という手順です。
毎回、色んな気付きがあり、勉強になっています。
2016年9月の第11回「事故事例研究」でも紹介しています。
http://www.greencity-f.org/article/15464206.html
最近は事故事例のほとんどを、スタッフしおりんが集めてくれています。
(私は年に2〜3件くらい…?)。いつもありがとう!
森づくり団体や自然学校、環境学習施設、公園の指定管理者など、いろんな組織・団体の方におすすめしたい取り組みです。
志賀島縦断ウォーキングツアー中、イノシシの子ども「ウリボウ」が私たちの目の前を通り過ぎました。
右手の斜面をズドドドッと駆け下り、道路を横切り、左手の谷へ降りていきました。
「イノシシが見れた!」と喜ぶ声もありましたが、運営側としては一瞬身構える場面ですね。
野外活動の安全管理では、イノシシやシカ、サルとの遭遇も注意したいところ。
実際、最近の福岡市内のニュースでも
2024年8月 片江展望台でイノシシにかまれる事故(福岡市城南区)
https://www.youtube.com/watch?v=o8-SNzn5GHw
(2024.11.24.閲覧)
2024年11月 内野中央公園で男児がサルにかまれる事故(福岡市早良区)
https://www.youtube.com/watch?v=HQew2nG2b3k
(2024.11.24.閲覧)
などがありました。
九州にはクマが生息していませんが、クマ対策が必要な地域ではよりシビアかと思います。
環境省のウェブサイトには、イノシシによる人身被害の統計が掲載されています。
https://www.env.go.jp/nature/choju/docs/docs4/index.html
(2024.11.24.閲覧)
この統計には「狩猟や捕獲作業等に伴う事故」を除いた数値が記載されています。つまり、登山、犬の散歩、農作業中の事故などが対象。それでも2~3年に1件程度の死亡事故が報告されています。
狩猟にからんだ事故を含めるとしたらかなりの数になるかもしれません。
イノシシ被害防止についての具体的な資料としては以下が参考になります。
復興庁「避難12市町村における鳥獣被害対策」
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-4/wildlife/20190118111241.html
(2024.11.24.閲覧)
※ページ中程の「福島県避難12市町村イノシシ被害対策技術マニュアル」
130ページ以上にわたる詳細なマニュアルです。(余談ですが、原発事故と避難指示にともなってこのような状況が起きていることを、知っておきたいですね)
野外活動の安全管理としては、VI章の「人身事故防止マニュアル」とその後の事例集が特に参考になりました。
個人的に付け加えるなら「獣道を見分ける目」を養いたいと感じています。
道路や登山道と交わるように獣道の「断面」が出てくることがあります。うっすらした踏み分け道だったり、筋状に落ち葉が踏まれて地表が出ていたり、ヤブがかき分けられていたり…。
明らかにわかる獣道は判断できるのですが、気付けていないものも多そう。
下見の時など、気を付けてチェックし、事前の注意やガイド等に活かせたらと思います。
森の落ち枝や剪定枝を集めて焚き火する時。
枝の中には結構な水分が残っています。
火にくべていると、枝の中の水分がグツグツと煮えて、道管(水分を吸い上げる管)や師管(養分を行き渡らせる管)を通って、手元の「木口(こぐち)」、つまり「枝を切った断面の部分」から出てきます。
蒸気のような気体がシューっと出てきたり、ブクブクと泡がたったり。蒸気や泡がなくても熱々なこともあります。
木ってやっぱり「管(くだ)」なんですね。
長い枝の手元を火から離れているからと安心して掴もうとしたら、うっかり熱々の木口で火傷するかもしれません。ご注意ください。
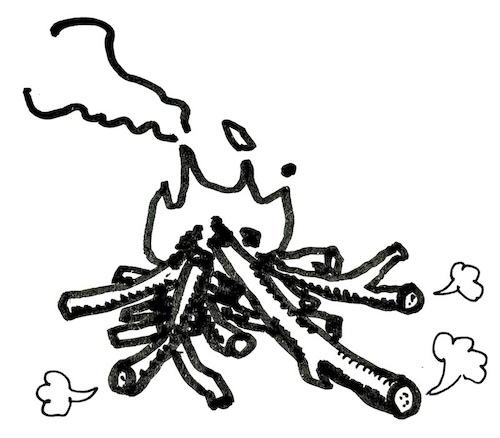
そんな注意点もありますが、森で拾った落ち枝や、森の手入れで発生した剪定枝、枯れ枝などで焚き火をするのは、森のエネルギーを有効活用しているような、ちょっとだけサバイバル体験をしているようなヨロコビがあります。
「これ燃えるかな?」と考えながら落ち枝を集めたり、手頃な大きさに切って太さごとに揃えたり、燃えやすいかたちに組んだりして、焚き火を楽しみたいと思います。
かなたけの里公園で行っている「はじめてのノコギリ・はじめてのたき火」
2023.11.15の様子 http://www.greencity-f.org/blog-post/376442
2022.12.7の様子 http://www.greencity-f.org/blog-post/373332
たき火関連の過去のコラム
第85回「焚き火と煙」2024年2月 http://www.greencity-f.org/blog-post/380540
第68回「風速5.0m/s」2021年12月 http://www.greencity-f.org/article/16445161.html
第58回「強風と乾燥時には焚き火をしない」2021年2月 http://www.greencity-f.org/article/16361101.html
第25回「着衣着火とSDR」 2018年1月 http://www.greencity-f.org/article/15862131.html
第24回「枝や串のこと」 2017年12月 http://www.greencity-f.org/article/15849816.html
先日、雷注意報が発令されている中、屋外イベントを実施しました。
中止も考えたのですが、
・現場の天候は晴れていたこと
・雷ナウキャストでは活動する雷雲が150kmほど離れていたこと
・すぐに逃げ込める施設周辺での活動だったこと
から実施としました。
事前にスタッフで共有したのは以下の2点。
・雷の音が少しでもしたらその時点で屋内に避難
・各自のスマホのトップに雷ナウキャストを置き、こまめにチェック
ナウキャストで黄色く示される活動度1以上の雷雲が近づいたら屋内に避難するつもりでイベントを進めました。実際は、雷の音を聞くこともなく、午前10時〜12時のイベントは無事終了。その日の夕方になってから、活動エリア周辺に雷雲がやってきました。
逃げ込める施設が近くにない場合や天候が急変しやすい山地での活動だったら、雷注意報の時点で中止や内容変更があり得たと思います。
それにしても、ナウキャストはありがたいですね。
気象庁が提供するリアルタイムに詳細な気象情報を提供するシステムです。
利用していない方はゼヒ!
下記ページで「雨雲」マークを押すと「雨雲の動き」、「雷雲」マークを押すと「雷活動度」が表示されます。

2023年7月、部活動帰りの中学生が熱中症で倒れ、その後、亡くなるという痛ましい事故がありました。ご家族や友人、周りのみなさんにとってたいへん辛い出来事だったと思います。
あらためてご冥福をお祈りいたします。
朝日新聞デジタル「熱中症の疑いで中学生死亡、1時間半の部活後帰る途中に 市が謝罪」
https://www.asahi.com/articles/ASR703JMHR7ZUZHB007.html (2024.08.12.閲覧)
1年ちょっとが経つ中、学校現場や行政では様々な対応や対策が行われてきたようです。報道に取り上げられた中からいくつか挙げておきます。
発生の翌月2023年8月に「米沢市小中学校熱中症対応ガイドライン」が更新されました。暑さ指数を計測する場面として「体育の授業」「運動会」に加えて「部活動」が追記され、指数が高い場合「中止」対応も明記されました。
米沢市「米沢市小中学校熱中症対応ガイドライン」
https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/11/1036/1/2037.html (2024.08.12.閲覧)
同じく2023年8月には、米沢市が遠距離通学の中学生31人の路線バス等の定期券代を全額補助することを決定しました。下校途中の事故だったことを受けての対応と思います。
朝日新聞デジタル「遠距離通学者にバス代を全額補助 米沢市、中学生の部活後の死亡受け」
https://www.asahi.com/articles/ASR8J6W4FR8JUZHB004.html (2024.08.12.閲覧)
今年2024年の4月には、市内学校に「暑さ指数」の観測機器を導入することが発表されました。米沢市と民間気象会社のウェザーニューズ社との包括連携協定により、半年間の試験運用を行うものです。
NHK NEWS WEB「米沢市 「暑さ指数」観測機器を市内の学校に試験的に導入へ」
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamagata/20240423/6020020346.html (2024.08.12.閲覧)
直近では2024年7月、熱中症を判定するAIカメラを市内7中学校に導入するといった報道もありました。
読売新聞オンライン「顔の表情などから熱中症のリスク判定、米沢市が「AIカメラ」を全中学校に導入へ…ポーラ化成工業開発」
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240626-OYT1T50221/ (2024.08.12.閲覧)
様々な対応、対策を行っている様子が伝わってきます。
それぞれの施策の良い点や改善点を活かしつつ、他の自治体、学校等に広まっていくと良いですね。
個人的に心に留めておきたいと思ったのは「一人でいることの危険」です。
複数でいればお互いにケアし合ったり、万が一体調不良の場合も助けを呼ぶことができたりできます。
が、一人でいた場合、熱中症の初期症状である熱失神であっても場合によっては致命的になりかねません。
イベントを実施する立場としては、休憩時間にちょっと離れている参加者の様子を伺ったり、イベントが終了して帰路に着く参加者の体調や表情を見ておくようにしたい、とあらためて思いました。
7月12日、朝日新聞さんがこんな労作を発表しました。
水難事故マップ
https://www.asahi.com/special/water-accident/
(2024.07.18.閲覧)
「海や川のレジャー事故発生場所を示した全国地図」です。
2013~22年の10年間の、海の事故8,329件、川や湖などの事故1,230件、合わせて1万件弱の事故がマップにプロットされています。
…作業、大変だっただろうな…。
ちなみに、海の事故データは海上保安庁の調査結果から。特定を防ぐために発生日時が含まれていません。
川や湖の事故データは河川財団が報道等から収集したもので、活動内容と当事者の年代が含まれていません。
河川財団さんのウェブサイトには、そのもとになった「全国の水難事故マップ(川・湖沼地等)」が公開されています。なんと、さらに10年ほど遡って、2003〜2023年のデータだそう。20年以上にわたって新聞やウェブニュースの水難事故の記事を収集されています。日頃の財団スタッフの方の地道な作業に頭が下がります。
全国の水難事故マップ(川・湖沼地等)
https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid118.html
(2024.07.18.閲覧)
両者のマップとも、示された発生地点の精度はバラつきがあるでしょう。その点については注意が必要です。ともあれマップの取りまとめに感謝しつつ、参考にさせていただきたいと思います。
グリーンシティ福岡では水辺のイベントをほとんど行いませんが、気を付けたいですね。
いよいよ学校は夏休みに入ります。
皆さんも身近な水辺などを確認してみて、水難事故の防止にご活用ください。

映画「シン・ゴジラ」で「政治家の責任の取り方は己の進退だ」というセリフがありました。「責任をとること」=「辞めること」だったらシンプルですが、実際はそれだけではありませんよね。
先日の環境保全活動の研修会でも、トラブルを起こした後の「責任の取り方」が話題になりました。「責任を取る」という言葉には重たくてしんどい、時には悲壮感あるイメージがありますね。
でも、具体的なタスクの集まり、と捉えた方がいいんじゃないかと思っています。
英語では「責任」に三つの単語があるそうです。それを手掛かりに整理しました。
森の保全活動のボランティアでうっかり道具を壊してしまった(例えば唐グワの柄を折った等)。そんな場面を事例に考えてみます。
(今回、「誰がそれをやるのか?」は一旦、置いておきます。団体自体、団体の代表者、指導していたリーダー、壊した本人など、状況によって様々です。)
遂行責任(レスポンシビリティ)
遂行責任とは、約束や予定を果たすための取り組みです。ボランティア活動ではノルマや納期がないことが多いので、この責任はあまり大きくない気がします。それでも、その日の作業に区切りをつけ、次回以降も活動を続けていくためにはいくつかやることがあります。
説明責任(アカウンタビリティ)
説明責任とは、トラブルの原因と今後の対策を説明することです。目的は再発防止。以下のような取り組みを行います。
賠償責任(ライアビリティ)
賠償責任とは、損害を受けた相手に補償することです。ボランティア活動中に起きたトラブルの賠償責任を個人に負わせることは、よっぽどの故意や悪質でない限りありません。第三者に損害を与えた場合でも、団体が加入する賠償責任保険で金銭部分はカバーされるはずです。それでも細かな部分や感情の部分で、「賠償責任」的な動きは残ると思います。
政治家の「辞める」=「責任を取る」という考え方がどれにあてはまるかよくわかりませんが、とにかく「約束や予定を果たすこと」「再発防止を心がけること」「損害を受けた人が補償されること」を考えたいものだな、と思います。