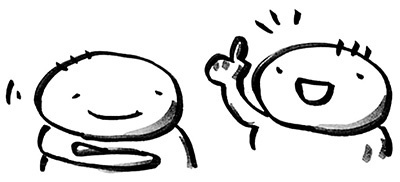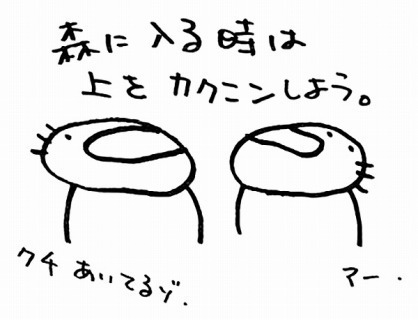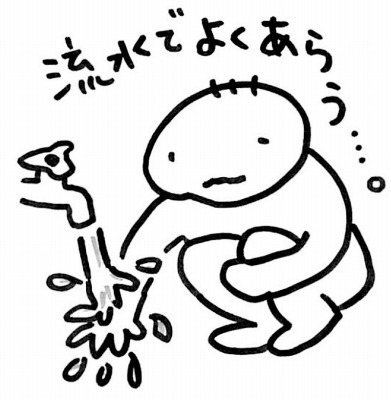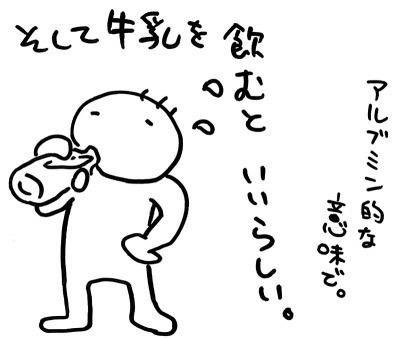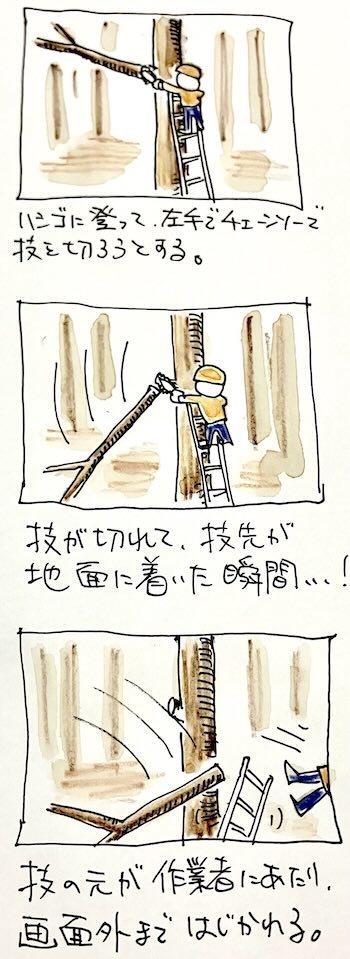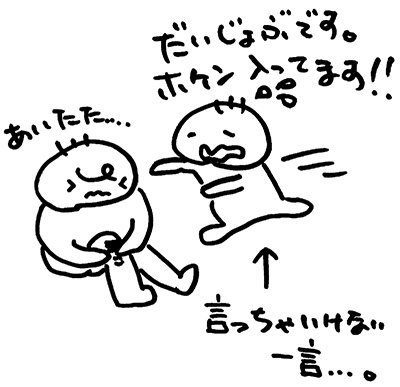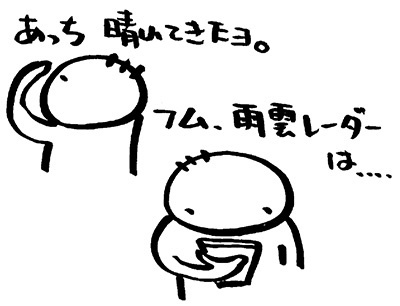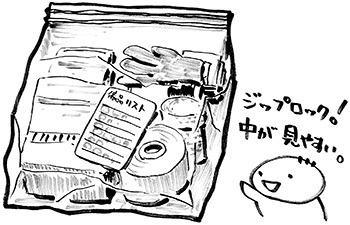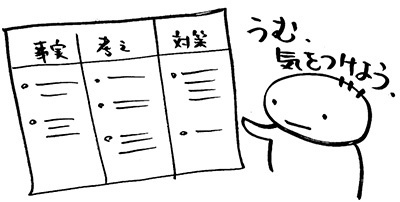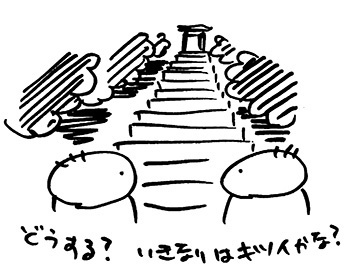先日(2018年2月6日),スペースX社が世界最大の推力を持つロケット「ファルコンヘビー」を打ち上げました。その動画を見ながら,宇宙開発の安全管理やチェックリストってすごそうだなあ,と考えていたら,2年前のX線天文衛星「ひとみ」の事故のことを思い出しました。
X線天文衛星「ひとみ」は2016年2月17日に打ち上げられ,3月26日に異常回転により破壊,その後,運用が断念されました。いくつもの問題やミスが重なったらしく姿勢制御できなくなった「ひとみ」。約310億円をかけたプロジェクトは宇宙の塵になりました。
JAXAは事故調査報告書の中の「今後の対策」の一つに「事業実施体制を見直す」と挙げています。その中に「プロジェクト管理に責任を持つ者と,成果の創出に責任を持つ者を別々に設ける(要約)」という趣旨の文章がありました。
分野は違いますが野外活動や環境活動でも大切な考え方かもしれません。
前者は,お金の管理や物品の準備,時間管理,参加者の心身の状態などに目を配りながら,着実に活動を遂行することを目指す役割。とても重要な存在ですが,これだけだと無事に活動はできるものの,面白みや充実感に欠けたり,モチベーションが下がっていくこともあるかもしれません。
後者は,より大きな成果を出したり,多くの参加者やボランティアに喜んでもらうために,もうひと押し!とがんばる役割。イベントを大きくしたり,次々と新しいプログラムに挑戦したりすることで,実績や話題になって良い面がある一方,安全管理が十分できなくなることも考えられます。
なんとなく「堅実な番頭さんタイプ」と「イケイケのリーダータイプ」を想像していますが,両者が一緒にいることがよい活動を行なっていくために大切なんじゃないかと思った次第。
異なる視点からの意見が得られることは,安全管理の面でも幸福なことだと思います。
参考文献:
MONOist「『ひとみ』はなぜ失われたのか(前編)」. http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1607/08/news018.html(2018.02.15.閲覧)
sorae.jp「X線天文衛星「ひとみ」はなぜ失敗したか」. http://sorae.info/02/201_06_21_astroh.html(2018.02.15.閲覧)